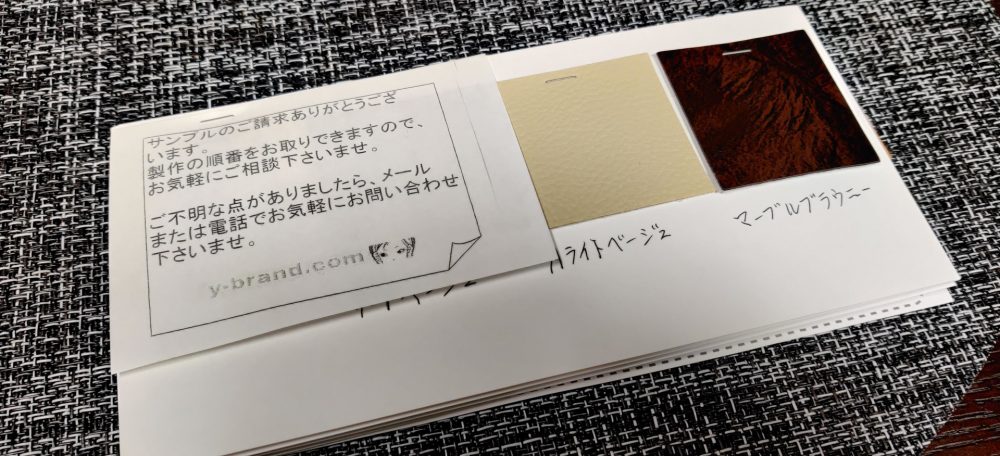前回、ミラジーノに取り付けるバックカメラを確認しました。
今回はこれを実際にミラジーノに取り付けたいと思います。
ですが、コペおじの手際の悪さゆえに何回か分けてブログに書きたいと思います
そして今回はバックカメラをリアドアに取り付けて車内に配線を引っ張るところまで書きたいと思います。
目次
まずはカメラの寸法を測るよ
今回はボディに穴を開けて配線を通す予定なので、配線が通る穴の大きさを調べておく必要があります。
また配線は通してカメラ本体は通さない程度の穴にする必要があります。
この投稿をInstagramで見る
横幅は26.6mm
この投稿をInstagramで見る
縦幅は25.5mm
この投稿をInstagramで見る
高さは26.2mm
本体サイズはだいたい26立方ミリメートルって感じですね。
これより大きな穴を開けないようにします。
この投稿をInstagramで見る
ケーブルが通っているネジのサイズは7.7mmですね。
穴のサイズは8~9mmぐらいで良さそうです。
カメラを取り付ける穴を開けていくよ
この投稿をInstagramで見る
寸法もわかったので、実際にやっていきます。
今回の被害車です。
当然のように書いてますが、今回のバックカメラの取り付け方法はボディに穴を開けてそこに配線やネジを通し裏をボルトで挟み込む感じです。
車を大切にしているオーナーさんからすると穴分けるとか言語道断ですね(汗
できる限り純正っぽく見えるようにするのでゆるして。
まずは裏のパネルを外します
この投稿をInstagramで見る
ミラジーノはお世辞にも高級車ではないですので、
リアドアの裏は鉄板をネジ止めしているだけです。
まずは鉄板を外してリアドアの内部にアクセスできるようにします。
ネジは大きめの2番で外せます
この投稿をInstagramで見る
パネルのネジは2番で外せます。
この投稿をInstagramで見る
ネジ自体は普通に止められているだけですので、
ドライバーで簡単に外せると思います。
ただ、パネルや止めている場所単なる鉄板ななので力を加えると曲がってしまうので気をつけてください。
2箇所だけネジ+クリップで止められています
この投稿をInstagramで見る
ネジを全部外しても2箇所だけプラスティックのリングが残っています。
これはクリップになっていてこれもパネルとリアドアを止めている部品の一つです。
内張り剥がしなどでまっすぐ手前に引っ張れば取れますが、
変に力が入るとパネルやネジ穴が曲がってしまうので注意してください。
この投稿をInstagramで見る
こんな感じのごく普通のクリップではあります。
金属が柔らかいのと、クリップが硬いのもあって取るのに苦労しました(汗
この投稿をInstagramで見る
クリップが取れると重力で落下してしまうので、
落とさないように気をつけてください。
この投稿をInstagramで見る
はい、外れました。
コペンと比べると100倍簡単でしたね。
バックカメラの配線を通す穴を開けるよ
この投稿をInstagramで見る
それでは穴を開けていきます。
あらかじめマジックで穴を開けるところに目印をつけました。
穴を開ける道具を写真に取るのを忘れてしまいましたが、
ホームセンターにあるステップビット(通称タケノコドリル)で十分です。
Amazon [ネセクト] ステップドリル
6.35mm六角軸 チタンコーティング インパクト対応[日本企画3年保証] (2枚刃 4-12mm 9段)
税込み1,158円
ただ、金属用のドリルでないと自動車の鉄板は良い鉄板を使ってますので穴を開けづらいです。
この投稿をInstagramで見る
あーあ、穴開けちゃった。もう後戻りできません。
カメラを取り付けてみるよ
この投稿をInstagramで見る
カメラの配線を通してみましたが、リアドアの内部で干渉することなく通すことができました。
この投稿をInstagramで見る
表から見た感じも、ナンバーフレートのフレームとカメラの余裕が0であたっていますが、いい感じに収まりました。
この投稿をInstagramで見る
遠くから見るとこんな感じです。
主張もなくさりげない感じでいいんじゃないでしょうか?
一発勝負でしたがいい感じに成功しました。
カメラ配線を室内まで引っ張るよ
それでは、ここからが本番です。
バックカメラの配線を頑張ってカーナビまで持ってくる必要があります。
配線の下準備を行うよ
この投稿をInstagramで見る
これがバックカメラとカーナビをつなぐケーブルです。
左側の黒いコネクタがカメラ側で、右側のよく見る黄色のRCA端子のコネクタがカーナビ側です。
で、ここでコペおじ、赤いRCA端子のコネクタがなんの役目をするのかわかっていませんでした。
この投稿をInstagramで見る
アップにするとこんな感じですね。
黄色のコネクタはビデオ信号が出るのはわかるのですが、
赤いコネクタが何に使うのかがわかってません。
でここでコペおじ、まあ中華製だから複数の製品で使い回せるように余分な配線があって必要ないんだろうなとこの時思い、
この投稿をInstagramで見る
コネクタが外れないようにと漏電防止の為にビニテープで束ねてしまいました。
これ、完全に失敗ですので真似しないでください……
リアドアの内側に配線を通していくよ
この投稿をInstagramで見る
でそんな失敗を未だに知らずな当時のコペおじはリアドアから車内に向けて配線を通していく作業をします。
写真の向きが横になっていて分かりづらいと思いますが、右側がドアの下側でカメラの配線が通っているところになり、左側がヒンジがある上側になります。
矢印の方向に配線を通していきます。
この投稿をInstagramで見る
リアドアの右上には純正配線が通っているグロメットがありますので、
今回のバックカメラの配線もここを通して車内へ引っ張っていこうと思います。
グロメットの中をカメラの配線を通すことはできないと思いますので、
ゴムパッキンに穴を開けてジャバラ部分を避けて通すことになると思います。
配線を通すところに針金を先に通していくよ
この投稿をInstagramで見る
配線コードを隙間を縫って通すのは至難の業ですので、
まずは針金のような硬いものを通してから配線を行ったほうが簡単にできます。
コペおじは前にも大活躍したホームセンターで買ったただの針金を使いました。
ただ今回の場合は針金だと隙間の障害物で簡単に曲がってしまい真っすぐ進んでくれないことが多かったので、ワイパーなどについてる平たい曲がりにくいワイヤーを使ったほうがいいと思います。
この投稿をInstagramで見る
15分ぐらいかけてグロメットのところまで針金を通すことができました。
リアドアの下から上へ配線をまっすぐ通せばいいので簡単そうに思えましたが、ピラー部分が全く目視できないのと、ドアが上へ跳ね上げて開くタイプで体勢が悪いのでかなり苦労しました。
針金が通ったときはすごく嬉しかったですね(笑
針金を差し込んだ側に通したい配線をくくりつけます
この投稿をInstagramで見る
針金が開通したら差し込んだ側に戻って、通したい配線を針金に巻き付けるなり、マスキングテープで固定するなりで針金に固定します。
あとは通した側で針金を手繰り寄せれば配線が通ります
この投稿をInstagramで見る
配線を針金に固定したら、今度は通した側に戻り針金を手繰り寄せます。
すると、反対側の針金が手繰り寄せた側に向かって進みます。
ここで配線を針金に固定していますので、一緒に手繰り寄せた針金を開通させた側に引っ張られて通ります。
そしてしばらくすると写真のように配線が出口から出てきて通すことができます。
これで、リアドアの下部分から上のグロメット部分まで配線が通せましたね。
あとはこれを車内に通せは今回のミッションは完遂です。
グロメット部は穴を開けてドアと車体を渡しました
この投稿をInstagramで見る
ドアから車内へ配線を通すのですが、今回は純正の配線が通っているグロメットに穴を開けてジャバラ部分を避けて通すことにしました。
なんでジャバラ部分を避けて通すかというと、カーナビに取り付ける黄色いRCA端子が太くてどう見ても純正の配線が通っているチューブの中を通せそうにないからです……
純正の配線の位置は借りつつ無理なく通す方法はグロメットに穴を開けるぐらいしか思いつきませんでした(涙
この投稿をInstagramで見る
同様に車内側のグロメットにも穴を開けて配線を通しました。
これで車内側に配線が伸びました。
今回の配線がドアの開け閉めで挟んだり、ドアに鑑賞しないようにジャバラにビニテープで止めておきました。
これでリアドアを開け閉めしているうちにバックカメラの配線が駄目になることはないと思います。
配線はCピラーの内張りの中にあります
この投稿をInstagramで見る
車内側のグロメットを通した配線はどこにあるかというと、
Cピラーの内張りの中にいます。
Cピラーの内張りの上部を少しだけこじって開けるとすぐに見つかると思います。Cピラーには後部座席のシートベルトが止められていてこれを外さないと完全には内張りを外せないので、天井とCピラーの内張りの隙間をこじって空ける程度に広げて配線を引っ張り出しました。
ちょっと無理矢理な感じなので真似される場合は気をつけてください。
次回は車内側の配線を通していきます
この投稿をInstagramで見る
ということで、一旦ブログは終わりたいと思います。
上の写真のようにリアドアの配線を今回は行いました。
配線した長さはごく僅かですが、針金がなかなか通らなかったり、グロメットに適度に穴を開けるのに苦労したりとこれでも2時間ぐらいかかってます(汗
次回は車内側の配線で、Cピラーからカーナビまで配線を通したいと思います。